   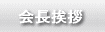      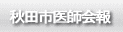    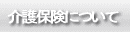    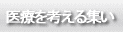  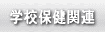  |
<春夏秋冬> |
発行日2024/08/10 |
| 平野いたみのクリニック 平野 勝介 | |
| リストに戻る | |
| 手形グラウンド(400mトラック) | |
|
1970年(昭和45年)5月、私と母はとりあえず大阪駅から寝台特急「日本海」に乗って秋田へ向かった。頼りない息子(私)に付いて来る母は、もっと不安だったろう。出発前、あらゆる人に助言を聞きまくり、爪楊枝は忘れないようにと言った人がいて、出発前夜それを準備していた。秋田に遠い親戚がいると言う友人から住所を聞いて保護者になってもらおうと思ったのだろう、着いたその日にタクシーでその人の住む土崎まで出かけた。その時に大学と手形グラウンドの間の県道15号を通り、その時に初めて手形グラウンドを見た。 私の高校時代、出身の三重県には公認の400mトラックは鈴鹿電通学園と言う学校の1ケ所だけで、しかし実の所このトラックもまともに検査が入れば公認されないポンコツであると1年生で補助員をしていた時に他校の先生から教えてもらった。高校時代、400mトラックは競技会でしか走ることはなかったので400mトラックへの憧れは強かった。入学後すぐに陸上競技部に入部して初めて練習に参加した時、他の部員が来るのを待ちきれずに400mトラックを走ってみた。最初のカーブをよそ行きのフォームで走り抜けた感激を今も覚えている。土のグラウンドがアスファルトより固いので注意するようにと先輩から言われ、常時数人のケガ人がいた。そんなことは関係なかった。グラウンドの3方は1~2mの土手に囲まれて、それらが草で覆われていてグラウンド内でクロスカントリーのような練習ができた。南側と北側には大きな落葉樹が並び夏は日陰を作って涼しく、我々の他、練習に来る高校や中学の休憩場所は決まっていた。その時の季節と同じく私の人生の初夏にあたる頃だった。グラウンドへはどこからでも入れるので、医師になっても夜中の12時からでも1時間の練習ができた。 40歳頃、自身の夏の終わりを感じ始めたのも、50歳過ぎの多臓器不全でICUのベッドに浮かんでいるときに見た人生の冬の始まりを悟る夢も手形グラウンドだった。 50年以上が過ぎてしまった。 今では400mトラックなど珍しくないどころか多くはタータントラックになった。雄和の県立競技場のサブトラックもタータントラックに改修された。アップの段階からタータントラックが必要なのだろうが、トラックを管理するために周囲を柵で囲い自由に入れなくなった。 当然、日常の練習もタータントラックが必要で、手形グラウンドも平成23年にタータントラックに改修され、周囲が柵で囲われてしまった。同時に西側を除く土手は撤去され、大きな木も半分以上伐採された。大きな環境の変化にも関わらずこのグラウンドに強い愛着を持って走るのは、このトラックの形状すなわち直送路の長さと曲走路の半径の微妙な割合が長時間をかけて体にきっと馴染んだためなのだろう。 |
| 春夏秋冬 <手形グラウンド(400mトラック)> から |