         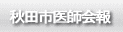            |
<ペンリレー> |
発行日2003/05/10 |
| 及川医院 及川光平 | |
| リストに戻る | |
| 愛犬ハチの死について | |
|
平成三年八月号の「ペンリレー」に「わが脚の友ハチ」を投稿した。ハチが一歳半ぐらいの、若犬の時だった。あれから十年余、短いような、永いような犬生だった。 平成十四年七月二日の夜、ハチは死んだ。十二歳七ケ月、この犬種としては長命ということだった。ハチの死について何かを書き残しておきたいと思ったが、何も書けないまま、時は過ぎていた。このたび、「ペンリレー」のバトンを渡されて、ようやくペンを執った。 K動物病院の手術台の上でハチは眠っていた。呼吸音も穏やかに、モニター心電図もよいリズムで、全麻はよく効いていた。ドクターは手際よく内視鏡をハチの口から入れて行った。ピンク色のきれいな食道がテレビ画面に映し出された。そして胃に入った。何やら薮の中に入ったみたいだ。吸引すると、少しガスが出た。急性胃拡張捻転症候群。これが致命的な疾病だった。 その日、早朝から腹が膨張し、歩けなくなった。苦しく、泣いているように吠えた。妻がハチを車に乗せてK動物病院に連れて行った。昼、私も行ってドクターの説明を聞いた。腹の単純写真などから、急性胃拡張でガスが溜まっているのだという。開腹手術が必要で、うまくいけば五分五分で治せる、術後は当分、毎日通院し、完全介護が要るということだった。私は、腹が決まった。そんなことまでして、ハチを無惨に生かしたくはない。妻も諦めたようだったが、一旦、家へ連れて帰りたいというので、麻酔が効いて、点滴で静かに眠っているハチを車に乗せて帰った。 午後、リビングで横たわっていたハチは又、苦しみの叫びをあげ始めた。それは私たちには耐えるに忍び難いものだった。夕方、診療を終えて、妻と事後のことを相談しているうちに、妻もハチの寿命をわかったようだった。 ハチの病院に電話した。ドクターに事情を話し、これから連れて行くこと、開腹手術はしないこと、全麻で、できるだけガスを抜いて欲しいこと、それは遠くにいる娘たちにも了解してもらうためのもので、最終的にはハチを楽にしてもらいたいこと、などを頼んだ。ドクターは了解して待っていた。外はまだ明るかったが、小糠のような雨が降っていた。 手術室はライトが煌々と光っていた。手術台のハチの傍らで、私は杖をついて長い間立っていた。内視鏡の所見と、ドクターの説明で妻も私も納得した。妻は、私に任せるという目配せをして手術場の外へ出た。私は、おもむろに「終わらせて下さい」と言った。ドクターは頷き、呼吸器をはずしますよと念を押した。濃い麻酔薬が注射されて間もなく、ハチの呼吸は停止した。 壁の時計に目が行った。午後八時八分を指していた。偶然なのだろうが、ハチは、八時八分に成仏した。妻を呼んだ。終わったよ、静かに逝ったよ、それだけ言うのが精一杯だった。ドクターと、時間外遅くまで働いた二人の若い助手たちにお礼を述べて、未だ暖かいハチを車に乗せ、病院を後にした。外は既に暗かったが雨はやんでいた。 リビングの座敷用のテーブルの上に、薄い夏がけに繰るんでハチを横たえ、クーラーをつけ、生前のハチの写真と、若い頃、柴犬全国展覧会でもらった栄光の賞状を飾り、線香を点した。目を閉じたハチを相手に、夜遅くまで冷や酒をすすり、ハチの端整な寝顔を見て、十二年間の幾つかの情景を想い起していた。 ハチの晩年、私の脚が不如意になり、ハチとの散歩がままならなくなった。一時、杖をついて一緒に歩いたが、冬場は無理だった。毎朝、きまった場所に座って、じっと私を待っている姿があった。出て行って、老いたハチの目頭の涙を拭き、全身にブラシを当てるのがせめてもの私の出来ることだった。ハチの耳が遠くなり、視力も落ちた。嗅覚でさえ衰えた。庭からリビングに入るところの縁台に上がれなくなり、幾度も試みて失敗し、芝生に転げ落ちた。縁台を新調して低くした。飼主としての義務を果たせなくなったことで、私は、老いてゆくハチの姿をみるにつけいとおしさが増した。 翌朝、一番機で、ハチと仲良しだった末の娘が来て、悲しみの対面をした。そして、朝な夕な、「おはよう」「さよなら」のあいさつ吠えをして、可愛がってもらっていた看護婦、事務員、そしてハチの散歩をしてくれたお姉さんたちも、ハチと対面して線香をあげてくれた。 今、パソコンのディスクトップに若い頃のハチの勇姿が画面一杯に映っている。今にも、ハチが、その冷たい鼻先を、私の頬に押し付けてくるようだ。ハチは死んだが、こうして毎日逢っている。私の心にまだまだハチが生きている。 次回は、相馬譲二先生にお願いしました。 |
| ペンリレー <愛犬ハチの死について> から |