         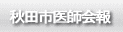            |
<ペンリレー> |
発行日2007/09/10 |
| 並木クリニック 熊谷暁子 | |
| リストに戻る | |
| 私のこれまで | |
|
午後の診療時間が始まってすぐ、まだ昼休みぼけの頭の私に「中通の川原先生からお電話入ってます』とのコールがあった。すぐさま受け取ると、「川原です。ちょっと頼みたいことがあって」といつもとかわらぬ声。 医師会ペンリレーの依頼と聞いて尻込みはしたものの、何しろ私は川原先生には頭があがらない。医師になって一年目の研修先であった能代の病院で、私の直属のオーベンの一人が川原先生であり、先生にとっては初めてのネーベンが私であった。私の医師としての土台を丁寧に耕してくれ、水や肥料をせっせと与え、育った芽が誤った方向に伸びると修正を加え、時には嵐を自ら巻き起こして喝を与え、と愛情いっぱい育てて頂いた。 今も先生に会うと、その頃の気持ちのまま、懐かしさと背筋が伸びるようなしゃんとした気持ちになる。一日一日が無我夢中で外来と病棟を駆け回り、共に汗して働き、語り、悩み、落ち込み、泣き、笑い、そして呑み!充実した毎日であったことにとても感謝している。 あれから13年が過ぎ、今の私は結婚し、二人の子供に恵まれ、子育てをしながら市内の有床診療所の勤務医として働いている。今、女性医師の勤務問題について盛んに議論がなされているが、まさにその渦中である。私が子供を持ちながら働くジレンマを抱えながらなんとか今に至っているのは、周囲の理解と協力に他ならない。 そんな私が、丸々専業主婦になった時期があった。2001年春から2年間、夫の留学に伴って家族4人サンフランシスコでの生活であった。ちょうど留学が決まった頃、私は二人目の子供を妊娠中であり、産後は仕事に復帰する予定だったのを変更して慌ただしく渡航準備を終え、3歳になったばかりの長女と生後4ヶ月の次女を連れての出発だった。夏休みの1週間以外にまとまった休みなんてとったことがないコテコテの医師生活から専業主婦?ポケベルフリー!の状態にいきなり突入したのである。 私は着いてから1ヶ月余、軽く鬱状態になってしまった。朝、夫を送り出すと夜までずっと子供らと三人だけ、24時間ひたすら子供と一緒の本当の専業主婦生活は想像をはるかに超えて大変だった。 これが日本であれば、頼れる母、保育園、友人とツテはあるのだが、一人の知り合いもいないところに母子三人ポーンと投げ込まれたのである。慣れない育児に疲労困憊、使えない英語にイライラ、子供は子供で環境の変化と親の不安定な心境に敏感になり、夫のいない日中は三人で大泣きしたこともあった。窓からシャボン玉を飛ばしながら歌う長女をみるだけで号泣、母からの国際電話に号泣、夫の「ただいま」という声に号泣といった具合である。 ところが、たまたま週末に買い出しに行ったスーパーで一人の子持ちの日本人女性とお友達になってから、あれよあれよという間に心境も一転。適応してからは早かった!長女がプリスクールと呼ばれる保育園に入園してからはあっという間に交遊半径が広がり、子供がいたからこその新しい世界が開けたのである。俗にいうママ友達という親友ができたのは私の財産です。ましてや留学先のスタンフォード大学は、大学が存在するパロアルト市自体が学園都市のようなもので、周囲一体とても治安が良く、物価が異常に高いことを除けば、いうことないくらい住みやすい町であった。西海岸の気候は過ごしやすく、夏場の気温は35度を超えるもの湿度が低いためにカラッとしていてクーラー要らず、また冬も温暖で当然雪も降らない、雨も滅多に降らず、抜けるような青空が毎日広がっていた。夫なんかは、多少ラボ内の人間関係でつまずいても、実験のデータが思うようにでなくとも、青空を見上げるだけで吹き飛ぶとなんともかわいらしいことを言っていた。日本でいたらストレス解消には酒かパチンコしかなかった人がである(笑)。また日本製のものは食料品から書籍にいたるまで簡単にマーケットで手に入れることができる利便性も兼ね備え、不自由したのは広い湯船や温泉ぐらいであった。生活に慣れると、今度は運転免許。大の運動音痴である私は、車の運転も苦手、最大の難関が免許獲得であったが、これが予想外に一発オッケー。試験会場に行くのも子供を預ける手だてもなく、夫が子連れで送迎、実技試験では抱っこひもでママを求めて泣きわめく乳児をかかえ、肩に大きなマザーズバッグをさげ、隣には不安そうにしっかり手をつないでいる三歳の女の子を連れた夫が疲労困憊した様子で見送ってくれた。これが試験官の同情を誘ったのか、実にスムーズに試験が終わり、最後には駆け寄ってきた娘に「Mommy is a good driver」と笑顔でOKサインをだしてくれた。夫はアジア人の悲壮感漂う家族を演出した作戦だったと結果に誇らしげ?だった。日本では苦手だった駐車も突っ込めばいいだけだから非常に簡単、おまけに広いし、道幅も十分、渋滞もほとんどない、大きなワゴン車の運転は快適で忘れられず、今でも乗りこなせるような錯覚に襲われるが周りに止められている。免許をとると一気に行動範囲も広がり、生活も安定しハリが出て、育児も楽しくなってきた。アメリカはとにかく子育て中の母親には天国であった。まず他人と比べるという概念がないから、自分の子供だけの成長に没頭できる。一人歩きはいつかとか、1歳の平均体重は?なんて気にする必要がないから、下の子は特にとらわれるものがなくひたすら自分の感覚で育てたような気がする。スーパーマーケットでも公園でも、公共の施設でも、設備が非常に整っており子連れで尻込みするストレスがない。家族でアメフトや大リーグ、NBA観戦など、十分に楽しめたのには意外だった。また、イースターから始まって、独立記念日、ハロウィン、サンクスギビング、クリスマスと、子供だけではなく大人にとってもお祭り騒ぎのできる楽しい行事が目白押しで、どれも思い出に残っている。夫の研究が終わり帰国するときには、安堵感と一緒に、もうちょっと長くてもよかったなあとすっかりアメリカでの主婦生活にはまっていて、長女はお友達や先生に「l will be back soon!』と言いふらしていた程馴染んでいた。帰国時には夫とともに既に次の勤務先が決まっていたため、感慨にふける暇もなくあっけなく主婦生活にピリオドがうたれ、そして勤務先では懐かしのオーベン川原先生がいたのである。2年間のたるんだブランクを取り戻そうとすればするほど、思うように仕事ができない子持ちのジレンマと限界を感じ、ストレスとしわ寄せが家族にじわじわと広がり、悩んだ末に私は外来中心の勤務医という形態で働く道を選び、今に至っている。大学病院で働く夫の話を聞くと、高度生殖医療もやってみたいし、いろんな手術にも参加してみたい。今でも夫の「手術やりたいでしょ」の言葉を素直に否定できない。というか一貫して患者さんを診ることにやはり憧れというかこだわりを捨てきれないでいる。が最近、私には私のできる仕事があるということにも気付き始めた。カリフオルニアの青空の下ハンバーガーをかぶりついている家族写真をみるにつけ、子持ちの制約も、専業主婦として過ごしたブランクも、何一つ無駄なことはなかったんだと素直に振り返ることのできる自分がいる。これから先も悩み、つまづくことがあったとしても私らしく医師という仕事を続けていきたいと切に思う。 最後に、今回このような執筆の機会を与えてくれた川原先生、そしてこれまでの暖かくご指導頂いた諸先生方に改めて感謝の気持ちを伝えたいと思います、ありがとうございました。 次回は、大学時代からの親友で,今は小学生の子持ちの母となった、渡邊亜紀子先生にペンリレーのバトンを渡したいと思います。 |
| ペンリレー <私のこれまで> から |