         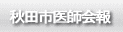            |
<ペンリレー> |
発行日2006/09/10 |
| 秋田組合総合病院 福田二代 | |
| リストに戻る | |
| 病気が私に教えてくれたこと | |
|
昨年私は、腹部の手術を受けた。 検診で便潜血が(+)、(-)であった。患者のデータだったら決して見逃さない重要な警告であるが、自分のこととなると忙しさにまぎれて、一年半も放置してしまった。もっと素直に、謙虚になるべきであった。 ある日、突然原因不明の激しい股関節痛があり、一夜のたうち回った。翌日の血液検査は進行した鉄欠乏性貧血で、消化管出血が長い期間続いていたことを示唆していた。内視鏡にて、予想した通り結構なサイズの腫瘍が見つかった。医者の不養生を地で行っていた私に大きな警告を与えてくれたあの激しい股関節痛は一晩で消失したが、果たして何だったのだろうか、と思う。折しも10日後に大学の同級会が犬山市で開催されたので夫婦で出席し、クラスメイトに別れの挨拶をした。以来、ずっと忌避していた飛行機に抵抗無く乗れるようになった。 摘出標本の病理組織も自分の目で確認し、これなら3年程度か?、と考えて若干ながら生き方を変えた。 医者になって36年、毎日がメメントモリ(memento mori、なんじは死を覚悟せよの意味で、死の警告。あるいは死の象徴としての髑髏)を意識させる環境であった筈なのに、自分自身にとってはそうでもなかったということ。 また、緩和医療に携わって3年、死に直面している人達と毎日接していても、やはり患者の死はガラス越しの事象に過ぎなかった。「太陽と死はみつめることは難しい」と言われるが、私もそう思う。しかし、自分も病気を得たことで、死を語れる仲間として、ほんの少し、やっと二歩ほど前に踏み込める様になった気がする。 昨年、私が診断を受ける前のこと、人生の最期の時間を生まれ故郷の秋田で過ごしたい、と小型ジェット機をチャーターして、ロンドンから秋田まで帰ってきたイギリス暮らしの、46歳の看護師のお世話をする機会を得た。ロンドン大学での最後の入院の際、有名な腫瘍専門医である主治医からもはや治療の対象ではないと宣告されたと言う。彼の地はホスピスの発祥の地でありながら、緩和ケア的配慮は少なく、とても辛く耐え難かったことで帰郷を決めたのだという。私どものもとで症状緩和はかなり旨くいった、彼女は満足して旅立った、と思っていた。しかし、彼女は看護師に「先生の治療方針が分からない」と漏らしていたとの事である。彼女の病床はわざわざロンドンから司祭が掛けつけたりしてとても賑やかであったが、死に行く人の心に寄り添うと言う細やかな配慮は今一つ不足だったのだろう。 「死」を学問のレベルにまで高めたのは、スイス生まれのエリザベス・キュブラー・ロスと言われている。この人が死ぬ時はどんな風なのだろうと以前から興味を持っていた。一昨年、彼女が亡くなったあとNHKは特別番組を放映した。啓発されて彼女の著書5冊ほど求めて読んだ。生い立ちを知り、第二次世界大戦の体験談を読んで彼女の一面が分かった気がする。開放直後のアウシュビッツにも立ち寄っている。彼女にとって、死は常に傍にあるものだったのだ。晩年、降霊術や臨死体験などに関っていくうちに周囲の人々が次第に離れていったとのことであったが、彼女は自分の信念を一切曲げることはなかった。炎の如くに燃えた恋の後に結ばれたご主人さえも彼女を止めることは出来ず、静かに去っていった。彼女は何回かの脳卒中の発作の後で亡くなったとのことであるが、がん患者としての最期を体験してもらいたかった。彼女は、はかない命と知らされ、打ちのめされている人たちと、死について会話することが本当に出来たのだろうか、と私は思う。 本論とずれるが、彼女の著書の中に興味深い文章があった。卒業したばかりの青年医師の給料と経験10年目の自分の給料とに3倍にも近い差があったという行である。女医が如何に冷遇されているのか、と激しい怒りを叩きつけている文章を見て、彼女の気性と当時のアメリカの医療の一端も知ることが出来た。 |
| ペンリレー <病気が私に教えてくれたこと> から |