         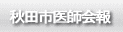            |
<ペンリレー> |
発行日2005/02/10 |
| 沓沢医院 沓沢貫之 | |
| リストに戻る | |
| 七面鳥 | |
|
これはすべてフィクションで文中の私は作者自身ではありません 毎年のようにやっている小学校の同級会だが、去年は卒後70年の節目の年と云うことで、その旨の案内状を出したら「5年生の時、お宅の七面鳥に追っかけられて、みんな泣きながら逃げ帰った。」と云う返事が来た。オンドリが羽を広げて向かってくると、女の子ならやはり怖かったにちがいない。 自宅の裏手に大きな溜池がある。昭和6年、当時村でただ一人の鉄砲打ちの五平じいさんは、ここを11月1日解禁日の最初の狩場にしていた。午前4時前、まだ薄暗い水面に霧が深く漂っている。所々黒い点々がかすかに見える。マガモの集団だ。近所の子供達は土手から頭だけ出してそれを数える。突然対岸の山手の木陰から水面すれすれに白い線条が走る。撃った瞬間である。黒い背がひっくり返って白い腹がでる。命中だ。少しおくれて銃声がこだまする。鴨は一斉に飛び立つ。それを狙って又2発3発。やがて霧がはれて水面が見えはじめると猟犬が泳ぎ、獲物をくわえて来る。じいさんは次の猟場に急ぐ。 池はもとの静寂にかえる。狩は終った。これからが子供たちの出番である。水辺の物陰に隠れて、手負い鴨の上陸を待つ。併しすぐ近くに来ても捕らえる事はなかなか出来ない。弓や吹き矢は仕掛がおおげさで、すぐ気付かれてしまう。空気銃がほしい。至近距離だと頭を射抜ける。Kデパートに11円50銭で出ていると云う。親にねだってみたが一蹴された。自分で銭を稼ぐしかない。 私は五平じいさんの助言で七面鳥を飼うことにした。肉も卵も銭にしてくれると云う。早速F町の親戚からつがいを貰った。放し飼いである。村里の開業医だから敷地の広さは十分で、しかも土塁に囲まれている。その大半は小松や潅木が点在する草地で、飼育には又とない環境である。 七面鳥は、鶏のように一粒一粒こせこせ拾うのではなく、口を大きくあけて一気に飲み込む。1つ小屋の中でも餌を争って鶏をいじめたりはしない。おうようである。そのおうようさが時には暗愚にみえることもある。大きな図体でヒヨコを踏み潰し、ピイピイ鳴いているのに知らん顔である。そのくせ、メンドリ達にはやさしくて、いつもよく警護しているようにみえる。 飼い主の私には従順で、名前のように、赤くなったり青くなったりする首を掴んでも抵抗はしない。表面には伸縮自在な毛のない厚い皮があって皺くちゃだが柔らかい。中は芯があってかたく異様な感じである。低温なのも気味が悪い。後年私は持続性勃起症で苦しんでいる患者を2例手掛けたことがあるが、強いて云えばこんな感触である。 小振りで見ばえのしないメンドリは控え目で、すべて夫まかせのように見える。交尾の時間が長いのとは関係ないだろうが、決して多産系ではない。それに、卵をかえすのが実に苦手で、オンドリの呼び声に、抱卵の身も忘れて巣を離れる始末で、嫁ならさしずめ姑のカモになるタイプである。私は常に鶏にだかせていた。卵は大きいので6個位が限度である。 ある日、間も無く孵化なのに、空巣になっているのはおかしいと、手を伸ばして卵を探したら、大きな青大将が腕に巻きついてきて目の前で舌を動かしていた。頭を叩き潰して口から皮を剥ぎ、飲まれた2個の卵はぬるま湯でよく洗って丁寧にふいてから巣に戻しておいたら、幸運なことにちゃんと孵った。蛇の身は、その田楽とドブロクが大好きな隣のごんじいにやった。連れのばあさんはドブロク造りの名手だったが、酒造りが何故悪いのか、留置所に何故入るのか、合点がいかぬまま正義?を叫び続けて死んだ。 母に蛇のことを話したらマムシでなくてよかったと言う。マムシはこの辺には一匹もいない。子供達がマムシ狩りをして換金し始めてから、もう何年もなるからである。昭和7年11月3日の朝、小屋の戸を開けたらプーンと死臭がした。若鳥6羽が全滅、その母親は首をやられて重態である。 かって私は祭の見世物小屋で、蛇の群れの上に投げ込まれた一羽のヒヨコを見たことがある。箱の中で瞼を閉じ力なく首を上下して死を待っていた。母親も同じ仕草である。こりゃ一駄目だ。翌朝母親は死んだ。水も飲めずに死んでしまった。 あきらかにイタチの仕業である。イタチは血を吸うだけで肉は食わぬと云う。途方に暮れていたら、ぜんやんが、キツネ用の おとし を持って来てくれた。正式の名称は知らないが、細長の木箱で、奥の餌を引っ張ると、紐で手前の板戸が落ちる仕組である。餌は、残酷と思ったが敢えて七面鳥の首にした。 ぜんやんは徴兵検査前の近所の若者である。弓矢や吹き矢の作り方、カメバチの巣やアナグマの獲り方、かすみ網やけもの罠の仕掛け方、ツグミの焼き方やウサギの皮の剥ぎ方、又川舟の漕ぎ方からスズキの釣り方まで、里山での狩猟百般を手ほどきしてくれる。 最初の夜は野良犬がかかった。大きな赤犬なので五平じいさんは喜んだ。街の登山家に皮を頼まれていたと言う。二日目の黒猫にはかなり痛いお灸をしておいた。本命のイタチがかかったのは三日目だった。犬、猫、鼠とこんな所まで強者優先のルールがある。 前方の落とし蓋を静かに開けて、顔を出したら素早く下ろせとぜんやんが教えた。大きく開けると逃げられる。小さいと顔が傷む。中途半端な生殺しではスカンク同様、俗に云う イタチのセツナッペ(刹那屁) で箱が臭くて使い物にならなくなる。 箱の上に乗り蓋を少し上げたら顔が出た。この時とばかりおろすと首が見事に挟まっていた。庇を出す暇もないほどの即死である。2日後にまた捕った。結局全部で5匹捕ったが、2匹はタイミングが遅く、腰のあたりを抑えたので、相棒たちが放屁の前にと、めった打ちにしてしまった。顔が命の剥製である。これではとても売り物にはならない。逃げられたのは、わずか一匹だが、とてもすばしこかった。黄色だったと五平じいさんに言ったら、「それはテンじゃ。それ一匹でおつりが来たのに。」と残念がった。 いままでの貯金とイタチの代金で空気銃を買うことができた。鴨猟には、予想以上の威力を発揮したことは言うまでもない。 銃は親には内緒なので、目の触れない鶏小屋に隠して置いた。所が翌年の夏、泥棒が入って鶏とともに盗まれてしまった。 併し盗人はすぐ捕まった。鶏を五平じいさんに売りに来たやつがいた。じいさんに諭されて、銃を出しながら「ちょっと借りたかった。ごめんなさい。」と言う。見れば同じ年頃の少年である。話しているうちに、3日前、仲間と一緒に盗みに入った西瓜畠の息子と判った。西瓜畠は大川の向かいにある。川向いは学区が違う。舟で行かねばならない。 悪ガキ同士妙に気があって、大げさに言えば肝胆相照らす仲となり、銃は秋まで貸す事にした。親交が続いていたが、残念ながらビルマで戦死。陸士を出て有能だっただけに、惜しい男を亡くしてしまった。 さて銃はかえったものの困ったのは置き場所である。我々だけでは埒があかず、結局ぜんやんに相談したら、「親に詫びて正々堂々と使うのが一番。」との事だった。殺傷嫌いの母に言っても反対は目に見えている。思いきって父に打ち明けた。所が父は金の出所を訊いただけで、すぐ許してくれた。頭上に雷が落ちると覚悟していたのに、全く意外であった。しかし間も無くその謎が解けた。 五平じいさんが父に、待望のカワウソの毛皮を持参した時、「これが捕れたのは、空気銃で川の向う岸から追ってくれたからだ。」と私の手柄にしてくれたからである。 実際は鮭の流し網を破って逃げようとしている所を、間一髪、丁度居合わせた五平じいさんが射殺したのである。幸運と偶然とが2つ3つ重ならないと、カワウソなんかは、なかなか捕れるものではない。「じいさん、私の為にウソを言ったの?」と訊いたら、「名前がカワウソだもの。」と笑っていた。 七面鳥はその後増えて近所の評判になった。顎をひき首をすえて、尾羽を広げ全毛を逆立て、左右の翼を地にすりながらのオンドリ達の威武競演の姿は、卓偉華麗にして典雅孤高、やはり荘厳の一語に尽きる。秋田が誇る画壇の巨匠、穂庵・百穂父子が好んで画題としたのも亦宜なるかなである。 歴史的に見ても人間に飼われてまだ日が浅いので、いざとなるとその野生味は猛々しく、闘争心も亦かなりなもので、特に赤いものに向かって行くあたりは闘牛に似ている。同級生が追われたのは、恐らく赤いものを身に着けていた為であろう。 夏のユカタは今と違って藍一色だったから間題はなかったが、当時ご婦人の中で流行のアッパッパと称するものでは、赤い模様はやはり禁物であった。ある日裏の方で悲鳴が聞こえた。オンドリが掃除婦のアッパッパを攻撃している。「服地が破れ、お尻が赤く腫れあがって血がにじんでいた。」と母が言った。こんな事故を防止する為に嘴の先を切る飼い主もいると聞く。 頭をつかめばよかったが、棒切れを拾って追い払おうとしたら、運悪く頭に当たってしまった。さしたる衝撃ではなかったが、はずみとは恐ろしい。異様な声を発してぐるぐる廻りながら、やがてばったり倒れてしまった。両足をのばして痙攣している。 その奇声を表で聞いたメンドリが、8メートルもある母屋の屋根を飛び越えて、斃れたオンドリのそばに駆け寄った。七面鳥が飛ぶのを見たのは、後にも先にもこれしかない。「カンフル。」看護婦が持ってきたのを背中に注射した。注射は昆虫採集でお手のものである。 その1月前、私は鶏の頭を出会い頭に下駄で蹴った事がある。この時も全く同じ症状だったが、父がカンフルを注射したら、忽ち走り去った。私は七面鳥も勿論、蘇生間違いなしとふんでいた。併しその思わくとは裏腹に、今度は生きて帰りはしなかった。 メンドリはいつまでも死体から離れなかった。そう云えばイタチにやられたメンドリの羽を投げ捨てておいた時も、毎日毎日オンドリがその場に通い続けていた。鶏では見たくても見れない光景である。いや、当世人間社会に於ても、学ぶべき点多い情景であろう。 数年前お盆のころ、私は昔の看護婦の訪問をうけた。亡父に線香を上げたいと言う。 「カキさん、昔、親父が鶏にカンフルをしたの知ってる?」 「ええ、でも、あれはカンフルじゃありませんよ。ただの水でしたよ。」 「じゃ一、僕が七面鳥にカンフルを注射したのも知ってるよね」 「あれも水でした。」 私は一寸驚いたが、注射液の稀釈や保存のことを考えて納得した。 「父は何故そんなことをしたんだろう?」 「さあ、何しろ咄嵯のことですから、よくは存じませんが、あのまま何もしないで死んだら先、あなたあきらめ切れました?親ってみんなそんなもんじゃないかしら。」 カキさんが去ったあと、彼女の飲み掛けのお茶に、私の知らない少年時代が、もっと詰まっているような気がしてならなかった。ぜんやんは現在、東京S区の豪邸で夫人と共に悠悠自適、優雅な日々を送っている。91歳のはずだ。蒼然たる笠門を、私は上京の折、何回もくぐっている。会社はもう孫の代で、後顧の憂いはみじんも無い。 昨春訪問の折、客間の窓から、懐かしい声が聞こえて来た。七面鳥である。昔の声は山の風に乗っていたが、今は街の風に乗って聞こえてくる。 夫人の言うには、もう20年も前から飼ってると云う。近所から苦情がないのは、屋敷が広いせいであろう。これまで一回も気づかなかったのは、たまたま鳴かなかったのか、それとも聞こえなかったのか等といぶかっていると、 「あの頃のことが忘れられなくてね。」 私は胸に込み上げて来る熱いものを感じた。かっては兄ともしたった男の懐郷の情溢れる言葉である。70何年も昔のことが昨日のように甦える。七面鳥がまた鳴いた。 「やはり田舎はいいよ。」 ぽつりともらした堀善七郎氏のこの独語にも似た一言がなかったら、この駄文が日の目を見ることは無かったであろう。 「俊足内山忠司先生からのタスキだった鈍足で申し訳ない。でも次は、章駄天秋元辰二先生だから大丈夫。」などと、1月2日、3日の箱根駅伝の興奮からまだ醒め切れないでいる。 奇しくもトリ年(乙酉)の正月に筆を擱く。 |
| ペンリレー <七面鳥> から |